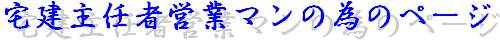●.公簿等調査 ●.現地調査 ●.設備等調査 ●.法令上の制限調査
依頼を頂いた物件の調査を始めるには、何から手を付けるのか?
どのような調査が必要か書いていきます。 |
| |
| 目 的 |
これから自分が取り扱う物件の真の所有者が誰なのかを把握し、他人の権利が付いていないか、その土地に建物を建築する際どのような制限を受けるかを調べ、買主の希望に合うものか否か損害を与えないようにして紛争の防止に努力する。この最初の調査を間違うと後を左右します。慎重に正確に把握しましょう。
|
| 公簿等調査 |
先日の受付の際得た情報を基に法務局にて調査資料を集めます。
●.公図
| 法務局にはブルーマップがありますので、地図を参考に対象物件だけではなく、隣地の地番もメモを取り、推測します。
|
| 住宅地図と公図の位置関係、要約書に記載された所有者、土地の形状等を比べ地番を確定します。
|
| しかし、公図は現況を正しく反映していないことの方が多いので、スケールアップも概算程度と認識した方が良いと思います。
|
| チェックポイントは、対象物件の地番確定と、図面上の情報方位、縮尺、閲覧日の記入があるかなどです。
|
| (昔と違い『閲覧』という形は出来なくなり、代わりに『登記事項要約書』という省略された書面になります。)
|
●.不動産登記簿
| 沖縄でもコンピュータ化が進んでおり『登記事項証明書』が普及しています。
|
| 公図と要約書で調べた地番を基に『登記全部事項証明書』の写しを取得します。
|
●.土地表題部
| なお、分筆等によりこの地積になった等の経緯も記載。
|
| 地図番号:殆んど『余白』となっていますが、ここに番号が付され ている時は、『17条地図』が備えられています。
|
コンピュータ化以前のバインダー式の登記簿について...
沖縄県では去る太平洋戦争により、宮古、八重山地域を除き、土地台帳及び土地台帳付属図面(地積図面)等は殆んどが消失したため存在しません。戦後、所有権認定事業が行なわれ作成された地図を基に、一筆調査図が法務局の地積調査分室という部屋に保管されているようです。
しかし、この線の引き直し事業があったにも関わらず、筆界未定地がまだまだ多く存在します。いや、戦争で資料が無いからこそ多くあるのかな?
この紛争を防止する為にも初期調査が大切になります。
受付⑧依頼者宅へ訪問の日までに登記済証や領収書等の準備を依頼しておきましょう。
|
| 登記事項証明書 | 法務局 |
固定資産税評価証明書
住民票、印鑑証明書 | 市区町村役所 |
| 登記済証、領収証 | 依頼者 |
|
|  | |